2011年02月24日
【コラム】MC51復活作戦! 最終日
G3って、こんなに性能のいい銃だったのか。
強化スリーブを組み込んだG3を撃って、最初に抱いたのはそんな感想でした。
首周りの剛性は、弾道に大して影響していない……と、前の日記には書きましたが、それはとんでもない勘違いでした。
前回試射したときには、弾道に細かな左右のブレがありました。ですが、風や給弾ノズル位置の違いで、多少のブレは誤差の範囲内だと思っていたのです。
ですが、首回りを強化した途端、左右のブレはまったくなくなりました。
試射した日は、わずかに横風が吹いていたのですが、多少の風などものともせず、弾はスコープの中心線に沿って、定規で引いたようにまっすぐ飛んでゆきます。
M14を髣髴とさせるような、素直で力強い弾道。
首周りをちょっと強化するだけで、これだけの弾道を得られる銃が、15年以上前の設計だなんて、ちょっと信じられないくらいです。
G3、特にフルサイズG3ユーザーの皆様。首回りの強化、文句なしにお勧めです。
高いお金を払って強化パーツを買ったり、あるいは、手間をかけて加工をしたりするのに見合うだけの価値はありますよ!
さて、銃本体は文句の無いレベルまで仕上がりました。
あとはまた、ちょこちょこと細かな加工を施してゆきます。
まず、見た目。

黒一色のG3は、タクティカルでかっこいいです。ですが、わたしが普段使っている民兵装備に合わせるには、ちょっと洗練されすぎです。
もっと野暮ったく、泥臭くなければ!
と、いうわけで、ちょっと塗装をして、今のSG-1然とした外見から、G3A3のような野暮ったい見た目に変更していこうと思います。
G3A3というと、かつて電動ガンで出ていた、細いハンドガードのモノが有名ですね。
あれは初期型のA3で、現用のものは、SG-1のものと同じ『SFハンドガード』という大型のハンドガードを装着しています。

これは、後期型と呼ばれる現用のG3A3です。
パキスタンなどでライセンス生産されているG3も、最近はSFハンドガードを装着したものが多いらしく、中東やアフリカなどの非正規軍においても、こうした後期型のA3が多く見られます。
これを目指して塗装して行こうと思います。

まずは、ストック、グリップ、ハンドガードをはずし、金属部品も取り外します。ハンドガードは接着剤で止められていますが、塗装のためにパッキリ二つに割りました。
その後、洗剤で汚れを落とします。
本当は、紙やすり等で表面を荒らしてやると塗装の食いつきがよくなるのですが、今回塗装するパーツはすべてシボ加工が施されているので、それでいいか、ということで今回は省きました。

パーツには持ち手となる棒をつけて、まずはサフを吹き付けます。
薄く、何回かに分けて塗り重ねると、塗装が垂れなくていい感じです。
サフが完全に乾いたら、目の細かい耐水ペーパーなどで、拭き取るようにして表面の荒れを削り取ります。
表面のざらざらした手触りがつるつるになったら、タオル等でぬぐい、今度は色を乗せていきます。
今回は、マルイのA3よりも少し濃いグリーンを選びました。
あまり明るい色だと、新品っぽさが出てしまう気がして、今回は野暮ったさ優先です。

乾いたら、ざらざらした表面をタオルでぬぐって滑らかにし、最後にトップコートを吹いて完成です。
さて、二つに割ったハンドガードを接着しなおします。
なるべく強力な接着剤を使いましたが、それでも、接着剤だけだとまたすぐ二つに割れそうな気がして、不安です。
裏側からテープで止めておこうか……とも思いましたが、どうせテープで止めるなら、ここにも小加工を施してしまおう、と思い立ちました。

ハンドガード内側にウレタンテープを貼り付けてみました。
組み込みがきつくなるくらいにウレタンを貼り付けると、ハンドガードを握ったときに前後にカタカタずれる感じは、完全になくなりました。
強く握ると、ちょっとギシギシ言いますが、この辺はプラですから仕方がないところでしょう。

と、いうわけで完成品です。
写真だと、せっかくグリーンに塗装したところが黒っぽく見えてしまいますね……。
ですが、内部、外見共に、納得のいくものに仕上がりました。
中学生の頃からの愛銃は、これで完全復活です。
今月27日にある定例ゲームで、初めてサバゲをやったときのことを思い出しつつ、使ってみたいと思います。
強化スリーブを組み込んだG3を撃って、最初に抱いたのはそんな感想でした。
首周りの剛性は、弾道に大して影響していない……と、前の日記には書きましたが、それはとんでもない勘違いでした。
前回試射したときには、弾道に細かな左右のブレがありました。ですが、風や給弾ノズル位置の違いで、多少のブレは誤差の範囲内だと思っていたのです。
ですが、首回りを強化した途端、左右のブレはまったくなくなりました。
試射した日は、わずかに横風が吹いていたのですが、多少の風などものともせず、弾はスコープの中心線に沿って、定規で引いたようにまっすぐ飛んでゆきます。
M14を髣髴とさせるような、素直で力強い弾道。
首周りをちょっと強化するだけで、これだけの弾道を得られる銃が、15年以上前の設計だなんて、ちょっと信じられないくらいです。
G3、特にフルサイズG3ユーザーの皆様。首回りの強化、文句なしにお勧めです。
高いお金を払って強化パーツを買ったり、あるいは、手間をかけて加工をしたりするのに見合うだけの価値はありますよ!
さて、銃本体は文句の無いレベルまで仕上がりました。
あとはまた、ちょこちょこと細かな加工を施してゆきます。
まず、見た目。
黒一色のG3は、タクティカルでかっこいいです。ですが、わたしが普段使っている民兵装備に合わせるには、ちょっと洗練されすぎです。
もっと野暮ったく、泥臭くなければ!
と、いうわけで、ちょっと塗装をして、今のSG-1然とした外見から、G3A3のような野暮ったい見た目に変更していこうと思います。
G3A3というと、かつて電動ガンで出ていた、細いハンドガードのモノが有名ですね。
あれは初期型のA3で、現用のものは、SG-1のものと同じ『SFハンドガード』という大型のハンドガードを装着しています。

これは、後期型と呼ばれる現用のG3A3です。
パキスタンなどでライセンス生産されているG3も、最近はSFハンドガードを装着したものが多いらしく、中東やアフリカなどの非正規軍においても、こうした後期型のA3が多く見られます。
これを目指して塗装して行こうと思います。
まずは、ストック、グリップ、ハンドガードをはずし、金属部品も取り外します。ハンドガードは接着剤で止められていますが、塗装のためにパッキリ二つに割りました。
その後、洗剤で汚れを落とします。
本当は、紙やすり等で表面を荒らしてやると塗装の食いつきがよくなるのですが、今回塗装するパーツはすべてシボ加工が施されているので、それでいいか、ということで今回は省きました。
パーツには持ち手となる棒をつけて、まずはサフを吹き付けます。
薄く、何回かに分けて塗り重ねると、塗装が垂れなくていい感じです。
サフが完全に乾いたら、目の細かい耐水ペーパーなどで、拭き取るようにして表面の荒れを削り取ります。
表面のざらざらした手触りがつるつるになったら、タオル等でぬぐい、今度は色を乗せていきます。
今回は、マルイのA3よりも少し濃いグリーンを選びました。
あまり明るい色だと、新品っぽさが出てしまう気がして、今回は野暮ったさ優先です。
乾いたら、ざらざらした表面をタオルでぬぐって滑らかにし、最後にトップコートを吹いて完成です。
さて、二つに割ったハンドガードを接着しなおします。
なるべく強力な接着剤を使いましたが、それでも、接着剤だけだとまたすぐ二つに割れそうな気がして、不安です。
裏側からテープで止めておこうか……とも思いましたが、どうせテープで止めるなら、ここにも小加工を施してしまおう、と思い立ちました。
ハンドガード内側にウレタンテープを貼り付けてみました。
組み込みがきつくなるくらいにウレタンを貼り付けると、ハンドガードを握ったときに前後にカタカタずれる感じは、完全になくなりました。
強く握ると、ちょっとギシギシ言いますが、この辺はプラですから仕方がないところでしょう。
と、いうわけで完成品です。
写真だと、せっかくグリーンに塗装したところが黒っぽく見えてしまいますね……。
ですが、内部、外見共に、納得のいくものに仕上がりました。
中学生の頃からの愛銃は、これで完全復活です。
今月27日にある定例ゲームで、初めてサバゲをやったときのことを思い出しつつ、使ってみたいと思います。
2011年02月22日
【メンバー】武内【紹介】

武内
高浜銃工の備品管理担当。
チームメンバーが所有している武器弾薬などをリストアップし、新人参加者や飛び入りの参加者に貸し出しを行う備品管理担当。
言うなれば高浜銃工のバルカン半島(火薬庫)である。
武内のバルカン半島たるゆえんは、役職だけではない。
多民族入り乱れるバルカン半島がごとく、ノリやテンションが時々によってまるで違うのである。
ゲームの数日前までは、嬉々として銃や装備品を準備し、パラベラム(戦争に備えよ)!! とばかりにゲームを楽しみにしていたかと思えば、当日、フィールドへ向かう車の中では、末期のベトナム戦線に送られてゆく若者のようにテンションが低い。
そうかと思えば、ゲーム中はまるでイギリス近衛兵のように、直立でざくざく恐れも知らずに敵陣に踏み入ってゆく。
そして帰りの車の中では、断食明けのイスラム教徒のようにハイテンションだ。
そんな、多民族ならぬ多人格の武内は、ゲーム中、敵にとっても味方にとっても読みきれないトリックスターである。
予想の斜め上を行く進軍で相手の意表を突き、「ここにいて欲しい!」と思う場所には、ひょっこり顔を出したりする。
しかし、前のゲームで大活躍したからといって期待をかけると、次のゲームでは突如弁慶の人格が覚醒したかのように直立で敵陣に切り込み、謎の立ち往生を遂げるなど、やはり読みきれないトリックスターである。
メインの装備は、ウッドランドピクセルのBDUに、ブラックのフリッツヘルメット。
銃は、最近購入したFA-MASを使っている。
しかしこのFA-MAS、すでにキャリングハンドルをぶった切って、G36のキャリングハンドル(ウグイス隊長の、かつての愛銃の残骸である)を移植しており、さらに今後、トリガー回りをP90のものに交換する予定だという。
もはや、フランスの銃なのかドイツの銃なのかベルギーの銃なのか、まるで判然としない。
役職から性格、使用する銃にいたるまで、まさに多民族多国籍多人格入り混じったバルカン半島なのである。
2011年02月21日
【A&K製 M249 MINIMI 分解と調整】
皆さんこんにちは!この度MINIMIを手に入れた「よざくやさくら」です。
近ごろ中華製の銃が良く目に付くようになって来ましたね、少し前までは中華製は不安ばかりでしたが最近は結構侮れなかったりします。特に大型の銃は格安で手に入りとても魅力的な存在で、ゲームが盛り上がるアイテムにもなります。
そんな大型銃が高浜銃工にもやって来ました!!
週末にチームメンバーと秋葉原に買出しに行った時にたまたま見つけたMINIMI(゚∇゚*) MKⅠ、MKⅡの両方がありA&Kの実物は初めて見たオオー(゚o゚*) 試しにとMKⅠを構えさせてもらうと、見た目ゴツイ割にそんなに重くなく、ストックとキャリーハンドルの形状が特に気に入った。MKⅡはストックの形状が体格に合わず構えにくかった・・・(・・*))んー
何度構えてもやっぱりMKⅠの方がしっくりきて、メンバーの押しと、隊長の支援があったので悩んだ末購入してしまいました!!陸自ミニミになるので装備にもピッタリだ。
よって、いつものあんまりさえないL96は長期休暇決定!(^∇^)アハハハハ!
まさか、この日ミニミを買うなんてこれっぽっちも思ってなかった、イベントは突然起こるもんですね
(ノ*゚▽゚)ノww
以下、各所レビュー&カスタムです。
おそらく、2011年2月現在の最新ロットなので参考になればと思います。
【外装】
まずは外装から。メタルがふんだんに使われていて、ストックやサイトなど可動部分も良く再現されていてとてもリアルで、特に実銃同様に銃身交換が出来る構造には感動!!重量は思ったよりも重くなくてバランスも良い方だと感じました。何かあるとすれば、塗装の耐久性がちょっと気になる程度かと。

【分解作業】↓↓↓
【メカボックス】
本体にはボルト2本で固定されているので取り外しはとっても簡単。肝心のメカボックスの中ですが、ネットのレビューだと緑色のグリスが無双乱舞しているとの事なので、メカボックス全バラクリーニングは欠かせません。本体から簡単に外れたメカボックスには多少のバリはあったけれどずっしりと重く耐久はありそうな感じでした。

注目点は、なんと言ってもバラさないでスプリングだけ交換出来る構造になっている事‼
素晴らしすぎる‼安全性とカスタム性の両方が備わっている!

スプリングガイドはベアリング仕様になっていて設計も考えられているようです。
下段はマルイ純正品

入ってたスプリング長は140mm(下段)でした。マルイ純正150mm(上段)に交換予定。

うわぁなんかハミ出てる(゚_゚i)・・・余計な所までグリス飛んでるし・・・(泣

やっぱり強烈な匂いの緑色のグリスがぁぁwww大量にぃw
きっと中でエイリアンがすり潰されたに違いない‼間違ってメカボに入っちゃただけだょね?

奴らの残骸をクリーナーで丁寧に洗浄して綺麗にしました。

明らかにズレてるシムもいましたww

ギアは思ったよりも綺麗な作りに見えます
シム調整、ピストン二枚目カット加工をしてモーターはマルイのEG700に交換しました。ただプラスチックパーツは不安が残ります。そこはマルイや社外パーツで対応です。
ネットで上がっているパーツと違う部品が多数組まれていたので、ロットの違いで色々改良されてるみたいです。特にメカボックスの内部は初期ロットから比べるとだいぶ変わってると思います。今後も改良が期待できそうです!
【スイッチ交換】
スイッチが弱いのは有名らしいので、OMRON製のスイッチを秋葉原のラジオセンターで調達しました。
さらにFET化するのが良いそうなのですが今回は様子見です。

【配線】
メインハーネスはやっぱり頼りなさそう・・ヒューズも形だけはそれっぽいのが付いていました。
マガジン配線は笑えるぐらい細く適当で中華クオリティー炸裂‼もやしみたいな線+ハンダ取れる寸前じゃねえかッwww 引き直さないとダメ、ゼッタイwww
基板はネットで見た茶色い物ではなく、コンパクトで緑色の物が付いていました。

【マガジンモーター交換】
給弾速度を上げ、動作を安定さるためにマブチモーター(ミニ四駆用アトミックチューンモーター)に変更して、もともと付いてたモーターには104コンデンサーが付いていたので同じように取り付けました。

【調整箇所】
・シム調整
・ピストン加工
・スプリング交換
・モーター交換
・スイッチ交換
・マガジンモーター交換
今回はゲームの日が近いので、部品が手に入りやすい以上の調整をしました。試射した所、異音もなく安定した飛距離と連射になりゲームでも期待出来そうです!
【調整目標】
ミニミニはハイサイクルでナンボだと思う人がほとんどだと思いますが、ハイサイクルではなく安定性と飛距離重視で仕上げたいと考えています。その為モーターはマルイEG700、バッテリーは8.4v(A&K定格は9.6v)の組み合わせです。早く一気に撃つのもアリですが、少しサイクルを落として長く弾幕を張った方が有効に使え、さらに耐久性も上がると考えます(ノーマルでも最近は十分早いと思うけど^^;
なにより!壊れない事がとても大事です(^-^)(「マルイのノーマル使えよ!」ってのは今回無しでww
次回のゲームで投入予定です!
MINIMI初期ロットからの先駆者様及び参考にさせて頂いたサイト様に感謝です/('-'*)
以上。ネタが出来たらまた上げますのでよろしくです。
近ごろ中華製の銃が良く目に付くようになって来ましたね、少し前までは中華製は不安ばかりでしたが最近は結構侮れなかったりします。特に大型の銃は格安で手に入りとても魅力的な存在で、ゲームが盛り上がるアイテムにもなります。
そんな大型銃が高浜銃工にもやって来ました!!
週末にチームメンバーと秋葉原に買出しに行った時にたまたま見つけたMINIMI(゚∇゚*) MKⅠ、MKⅡの両方がありA&Kの実物は初めて見たオオー(゚o゚*) 試しにとMKⅠを構えさせてもらうと、見た目ゴツイ割にそんなに重くなく、ストックとキャリーハンドルの形状が特に気に入った。MKⅡはストックの形状が体格に合わず構えにくかった・・・(・・*))んー
何度構えてもやっぱりMKⅠの方がしっくりきて、メンバーの押しと、隊長の支援があったので悩んだ末購入してしまいました!!陸自ミニミになるので装備にもピッタリだ。
よって、いつもの
まさか、この日ミニミを買うなんてこれっぽっちも思ってなかった、イベントは突然起こるもんですね
(ノ*゚▽゚)ノww
以下、各所レビュー&カスタムです。
おそらく、2011年2月現在の最新ロットなので参考になればと思います。
【外装】
まずは外装から。メタルがふんだんに使われていて、ストックやサイトなど可動部分も良く再現されていてとてもリアルで、特に実銃同様に銃身交換が出来る構造には感動!!重量は思ったよりも重くなくてバランスも良い方だと感じました。何かあるとすれば、塗装の耐久性がちょっと気になる程度かと。
【分解作業】↓↓↓
【メカボックス】
本体にはボルト2本で固定されているので取り外しはとっても簡単。肝心のメカボックスの中ですが、ネットのレビューだと緑色のグリスが無双乱舞しているとの事なので、メカボックス全バラクリーニングは欠かせません。本体から簡単に外れたメカボックスには多少のバリはあったけれどずっしりと重く耐久はありそうな感じでした。
注目点は、なんと言ってもバラさないでスプリングだけ交換出来る構造になっている事‼
素晴らしすぎる‼安全性とカスタム性の両方が備わっている!
スプリングガイドはベアリング仕様になっていて設計も考えられているようです。
下段はマルイ純正品
入ってたスプリング長は140mm(下段)でした。マルイ純正150mm(上段)に交換予定。

うわぁなんかハミ出てる(゚_゚i)・・・余計な所までグリス飛んでるし・・・(泣
やっぱり強烈な匂いの緑色のグリスがぁぁwww大量にぃw
きっと中でエイリアンがすり潰されたに違いない‼間違ってメカボに入っちゃただけだょね?

奴らの残骸をクリーナーで丁寧に洗浄して綺麗にしました。

明らかにズレてるシムもいましたww

ギアは思ったよりも綺麗な作りに見えます
シム調整、ピストン二枚目カット加工をしてモーターはマルイのEG700に交換しました。ただプラスチックパーツは不安が残ります。そこはマルイや社外パーツで対応です。
ネットで上がっているパーツと違う部品が多数組まれていたので、ロットの違いで色々改良されてるみたいです。特にメカボックスの内部は初期ロットから比べるとだいぶ変わってると思います。今後も改良が期待できそうです!
【スイッチ交換】
スイッチが弱いのは有名らしいので、OMRON製のスイッチを秋葉原のラジオセンターで調達しました。
さらにFET化するのが良いそうなのですが今回は様子見です。
【配線】
メインハーネスはやっぱり頼りなさそう・・ヒューズも形だけはそれっぽいのが付いていました。
マガジン配線は笑えるぐらい細く適当で中華クオリティー炸裂‼もやしみたいな線+ハンダ取れる寸前じゃねえかッwww 引き直さないとダメ、ゼッタイwww
基板はネットで見た茶色い物ではなく、コンパクトで緑色の物が付いていました。
【マガジンモーター交換】
給弾速度を上げ、動作を安定さるためにマブチモーター(ミニ四駆用アトミックチューンモーター)に変更して、もともと付いてたモーターには104コンデンサーが付いていたので同じように取り付けました。
【調整箇所】
・シム調整
・ピストン加工
・スプリング交換
・モーター交換
・スイッチ交換
・マガジンモーター交換
今回はゲームの日が近いので、部品が手に入りやすい以上の調整をしました。試射した所、異音もなく安定した飛距離と連射になりゲームでも期待出来そうです!
【調整目標】
ミニミニはハイサイクルでナンボだと思う人がほとんどだと思いますが、ハイサイクルではなく安定性と飛距離重視で仕上げたいと考えています。その為モーターはマルイEG700、バッテリーは8.4v(A&K定格は9.6v)の組み合わせです。早く一気に撃つのもアリですが、少しサイクルを落として長く弾幕を張った方が有効に使え、さらに耐久性も上がると考えます(ノーマルでも最近は十分早いと思うけど^^;
なにより!壊れない事がとても大事です(^-^)(「マルイのノーマル使えよ!」ってのは今回無しでww
次回のゲームで投入予定です!
MINIMI初期ロットからの先駆者様及び参考にさせて頂いたサイト様に感謝です/('-'*)
以上。ネタが出来たらまた上げますのでよろしくです。
2011年02月19日
【コラム】MC51復活作戦! 四日目
さてさて、MC51復活作戦、四日目です。
前回までのカスタムで、本体はほぼ完成しました。
しかし、スコープの傾きが著しく、照準として使い物にならなかったので、マウントリングを交換してみました。

ノーブランドのマウントリングです。
径1インチ、高さが20mmで、前回のような片手持ちのリングではないので、ゆがみは出にくいはずです。
試射した感じも、前回の片手持ちリングよりは傾きが改善されていました。
高さ20mmはマウントとしてはかなり高めですが、G3はフロントサイトポストが高いので、フロントサイトがスコープに写り込まないようにするにはこのくらいの高さが必要ですね。
着弾点の調整のためにスコープに角度をつけたりすると、20mmでもギリギリでした。
さて、本体、照準ともに完成したので、あとはちょっとした小加工を行います。
まず、G3の代名詞、首周りの弱さを改善します。
今のところ首周りの弱さが着弾に影響している感じはしませんが、フロント部分にスリングを通して持ち運ぶことを考えると、やはり心もとないと言わざるを得ません。
ゲーム中にスリングをかけたまま転んで、銃が真っ二つにでもなってしまったら洒落になりませんし……。
と、言うわけで、ホームセンターで手に入る素材を使って、お手軽に首周りの強化をしてみたいと思います。

用意するのは、二本のアルミパイプ。
外径12mm・内径9mmのパイプと、外径16mm・内径13mmのパイプです。
まず、外径12mmのパイプ、これをアウターバレルにします。

純正の亜鉛合金パイプと比べて強度が上がる訳ではありませんが、アルミパイプは軽量なため、フロントにかかる負担を減らすことができます。
ただ、亜鉛合金よりも柔らかい素材ですので、フロントサイト部分の芋ネジを締めすぎないよう注意が必要です。
さて、外径16mmのパイプはどこに使うかというと、バレル上部のコッキングレバーからフレームへ、背骨のように通します。

まずフロント側の加工です。
コッキングレバーの中へ、16mmパイプを挿入します。
コッキングレバーは16mmのパイプを入れるにはギリギリで、ただ押し込んだだけでは入らないので、プラハンマーなどで少しずつ叩き込んでいきます。

画像のあたりまでパイプがはまり込めば、コッキングレバー側は完成です。
あとは、フロントから突き出たパイプを70mmほど残してカットし、フレーム側に差し込めば、パイプが背骨のようにフロントからフレームまでを繋いでくれます。
これだけで、だいぶ首周りの剛性が強化されました。
バレルを掴んで持ち上げたとしても、フロントがしなる感じはありませんし、構えたときのギシギシ音もかなり改善されています。
と、いっても、ハンドガードがプラ製なので、まだ多少のギシギシ音は残りますが……。
この辺は、G3A3のような細身のハンドガードに換装すればある程度解決するでしょう。G3A3はすでに絶版品ですので、パーツを手に入れるのは難しいですが……もし手に入ったら、ぜひ付け替えてみたいと思っています。
さらにもう一つ、セレクターレバーに小加工を施しています。
G3のセレクターレバーはかなり大ぶりで、フルオートポジションにすると、トリガーフィンガーに引っかかるくらいフレームからはみ出ます。
右利きであれば、多少邪魔といった程度で済みますが、あいにく筆者は左利き。
フレームからはみ出たレバーが、グリップを握る親指に干渉して邪魔な上、しっかりグリップを握ろうとすると、無意識にセレクターに触れてセミオートポジションにしてしまうこともあります。
非常に使いにくいので、レバーの邪魔な部分をカットしてしまいました。

セレクターレバーの裏には、セレクターのクリック感を出すためのスプリングが入っているので、これを残したい場合、カットできるのは画像の位置が限界です。
切断面は面取りして、黒く塗装してあります。
最後に、中国軍のAK用スリングを取り付けて完成です。

さて、首周り強化&スコープの固定が完了したので、後日最終チェックも兼ねて試射をしてみるつもりです。
なにか異常が出ていなければいいのですが……。
同時に、整備しなおした多弾装マガジンの調子も見てみるつもりです。
前回までのカスタムで、本体はほぼ完成しました。
しかし、スコープの傾きが著しく、照準として使い物にならなかったので、マウントリングを交換してみました。
ノーブランドのマウントリングです。
径1インチ、高さが20mmで、前回のような片手持ちのリングではないので、ゆがみは出にくいはずです。
試射した感じも、前回の片手持ちリングよりは傾きが改善されていました。
高さ20mmはマウントとしてはかなり高めですが、G3はフロントサイトポストが高いので、フロントサイトがスコープに写り込まないようにするにはこのくらいの高さが必要ですね。
着弾点の調整のためにスコープに角度をつけたりすると、20mmでもギリギリでした。
さて、本体、照準ともに完成したので、あとはちょっとした小加工を行います。
まず、G3の代名詞、首周りの弱さを改善します。
今のところ首周りの弱さが着弾に影響している感じはしませんが、フロント部分にスリングを通して持ち運ぶことを考えると、やはり心もとないと言わざるを得ません。
ゲーム中にスリングをかけたまま転んで、銃が真っ二つにでもなってしまったら洒落になりませんし……。
と、言うわけで、ホームセンターで手に入る素材を使って、お手軽に首周りの強化をしてみたいと思います。
用意するのは、二本のアルミパイプ。
外径12mm・内径9mmのパイプと、外径16mm・内径13mmのパイプです。
まず、外径12mmのパイプ、これをアウターバレルにします。
純正の亜鉛合金パイプと比べて強度が上がる訳ではありませんが、アルミパイプは軽量なため、フロントにかかる負担を減らすことができます。
ただ、亜鉛合金よりも柔らかい素材ですので、フロントサイト部分の芋ネジを締めすぎないよう注意が必要です。
さて、外径16mmのパイプはどこに使うかというと、バレル上部のコッキングレバーからフレームへ、背骨のように通します。
まずフロント側の加工です。
コッキングレバーの中へ、16mmパイプを挿入します。
コッキングレバーは16mmのパイプを入れるにはギリギリで、ただ押し込んだだけでは入らないので、プラハンマーなどで少しずつ叩き込んでいきます。
画像のあたりまでパイプがはまり込めば、コッキングレバー側は完成です。
あとは、フロントから突き出たパイプを70mmほど残してカットし、フレーム側に差し込めば、パイプが背骨のようにフロントからフレームまでを繋いでくれます。
これだけで、だいぶ首周りの剛性が強化されました。
バレルを掴んで持ち上げたとしても、フロントがしなる感じはありませんし、構えたときのギシギシ音もかなり改善されています。
と、いっても、ハンドガードがプラ製なので、まだ多少のギシギシ音は残りますが……。
この辺は、G3A3のような細身のハンドガードに換装すればある程度解決するでしょう。G3A3はすでに絶版品ですので、パーツを手に入れるのは難しいですが……もし手に入ったら、ぜひ付け替えてみたいと思っています。
さらにもう一つ、セレクターレバーに小加工を施しています。
G3のセレクターレバーはかなり大ぶりで、フルオートポジションにすると、トリガーフィンガーに引っかかるくらいフレームからはみ出ます。
右利きであれば、多少邪魔といった程度で済みますが、あいにく筆者は左利き。
フレームからはみ出たレバーが、グリップを握る親指に干渉して邪魔な上、しっかりグリップを握ろうとすると、無意識にセレクターに触れてセミオートポジションにしてしまうこともあります。
非常に使いにくいので、レバーの邪魔な部分をカットしてしまいました。
セレクターレバーの裏には、セレクターのクリック感を出すためのスプリングが入っているので、これを残したい場合、カットできるのは画像の位置が限界です。
切断面は面取りして、黒く塗装してあります。
最後に、中国軍のAK用スリングを取り付けて完成です。
さて、首周り強化&スコープの固定が完了したので、後日最終チェックも兼ねて試射をしてみるつもりです。
なにか異常が出ていなければいいのですが……。
同時に、整備しなおした多弾装マガジンの調子も見てみるつもりです。
2011年02月18日
【メンバー】副隊長サラサ【紹介】

サラサ
高浜銃工の副隊長。
持ち前の社交性を生かしてゲーム中に他のチームと仲良くなることが多く、チームの交流の輪を広げるのに一役買っている。
チーム内でほぼ唯一、「突撃したい病」を患っておらず、敵の進行ルートを予測した、根気強い待ち伏せ攻撃を得意としている。特に有効なブッシュ(通称「巣穴」)を見つけるのが上手く、本気で隠れられると味方でさえその姿を見失ってしまうほど。高浜銃工のメンバーならば誰もが、サラサの待ち伏せに一掃されたトラウマを持っている。
サラサが隠れた後のフラッグ周辺は、さながら地雷原であり、味方アタッカーが散った後、大勢で攻め込んできた敵を単身で全滅させ、チームを逆転勝利に導くこともザラ。
しかし逆に、味方の突撃が成功してしまったときは、一人後方で暇をもてあまし、巣穴で虫やキノコをつついているうちにゲームが終わってしまうこともしばしばある。
最近は待ち伏せだけでなく、前線にも出てくるようになったため、今後、前線において隊員たちのトラウマを増やす日も近いと思われる。
装備は、一般的なウッドランドBDUにキラーキャップ。
メインウエポンはM4A1。一対多数の戦闘を行うことが多いため、フルオートで弾をばら撒ける銃を愛用している。最近はもっと軽量なスコーピオンに乗り換えたいらしい。
M4A1には、ゴム製の銃剣を装着している。単なる飾りではなく、アンブッシュ中に邪魔なブッシュをどかしたり、虫やキノコをつついたりする際に大活躍。
サブウェポンはクロームシルバーのデザートイーグル。巨大なデザートイーグルを片手で振り回す様はさながら『ニキータ』だが、重い、引っかかる、邪魔、等の理由から、最近はもっぱらセーフィティーゾーンに転がされている。
2011年02月16日
【メンバー】ちょこぼ【紹介】

ちょこぼ
役職……特にないです。
高浜銃工の雑用担当……かどうかは知らないが、良くも悪くもみんながやりたがらない仕事を任されることが多い。
正式な役職は特になし。役職決めの際、その場にいなかったのが運の尽きなのであった。
ゲーム中においても、やはり良くも悪くも他人が行きたがらない道、やりたがらない戦術を取る。
高い木によじ登って落ちたり、険しすぎて嫌われる道を一人で進んでいったり、チーム全員がフラッグの防御に回れば、一人だけ敵のフラッグめがけて走りこんだり……。
そうした奇抜な行動によって、良くも悪くも他人の意表を突くことが多い。
敵の意表を突いて思いがけず大活躍することもあれば、味方の意表を突いて敵と間違われ、大量のフレンドリーファイアを食らうこともある。
良くも悪くも、ゲーム展開を引っ掻き回すジョーカー的存在なのである。
装備は、森林ではやたらと目立つデザートカラーのBDUに、何も入ってないナイロンのスワットベスト。
武器は、G3SASやMAC10など軽量なものを好むが、その一方で足、脇、腰の三箇所にホルスターをぶら下げ、それぞれにサムライエッジを差しているため、せっかくの身軽さが半減している。
そもそも、なぜハンドガンを何丁も持ち歩いているのか、なぜすべてサムライエッジなのか、そんなに大量のゾンビと戦う予定があるのか、まったく分からないが、そうした理解不能なところこそがちょこぼ最大の武器なのかもしれない。
良くも悪くも未知数すぎるところが災いしてか、チーム内での立ち位置は、冒頭で述べたとおり良くも悪くもない。
2011年02月16日
【メンバー】よざくやさくら【紹介】

よざくやさくら
高浜銃工の会計担当。車も出せる。
隊の口座を一手に預かり、収支を管理する高浜銃工の会計担当。
お金が貯まるたびに「ミニガンが欲しい」とか「温泉旅行に行きたい」とか「ブローニングM2付きのハンヴィーが作りたい」とか、基本的に無駄遣いすることばかり考えている隊員たちから財布を守っている。
ゲームにおいても、その判断能力を駆使してメンバーを指揮し、勝利を掴み取る優秀な指揮官である。
特にフラッグアタックの手腕はすばらしく、よざくやさくら指示のもと、複数人で行う連携アタックによって、幾度も敵陣の旗を引き摺り下ろしてきた。
しかし、本人はどちらかと言うと指揮より突撃のほうが好き。時折、胸のうちに眠る大和魂が目覚めたかのように、特に追い詰められてもいないのに決死の突撃を敢行し、ゲーム開始数分で若い命を散らした挙句、セーフティゾーンに「恥ずかしながら帰ってまいりました」とばかりに帰って来ることもある。
まじめに指揮を執ってくれれば「神風」、無謀に突撃すれば「カミカゼ」なよざくやさくらの装備は、大和魂息づく(現)陸上自衛隊装備。
チーム内でもトップクラスにしっかりした軍装をしているため、活躍しているときの雄姿は息を呑むほど。写真栄えも素晴らしい。
メインで使用している銃は、東京マルイのL96。だが、本人としてはそろそろフルオートで撃てる武器に持ち替えたいらしく、隊長が89式に飽きるのを虎視眈々と狙っているとかいないとか。
今まであえてボルトアクションライフルを使っていたのは、三八式を手に戦った先祖たちの戦いを追体験していたのかもしれない。
しかし、ボルトアクションライフルで突撃して「撃ちてし止まむ」となったのはせいぜい第二次大戦まで。なるべく早く現用兵器を手に入れて、「カミカゼ」ではない突撃を見せてほしいと願うばかりである。
※先日の買出しにて、念願のフルオートウエポンを購入した。
それも89式ではなく、自衛隊仕様のMINIMI。
自衛官は、第二次大戦から現代戦へ、一足飛びに時を越えた。
2011年02月16日
【メンバー】隊長ウグイス【紹介】

「みんな、もっと無線使ってくれ」
ウグイス
高浜銃工の隊長にして、雑用にして、運転手にして、その他面倒くさいこと担当。
ゲーム開催日のすり合わせ、フィールドの決定や予約といった大きな仕事から、当日の運転や新人指導などという雑用まで、零細企業の社長のように仕事を兼任するチームリーダー。
隊員たちがそろいもそろって、ゲーム希望日のメールすら返さない超絶的な面倒くさがりであるあたり、その苦労が伺える。
ゲーム中においても、その隊長気質は健在。
味方の士気が低いときには、ゲームスタートと同時に全力疾走をかまし、チームの進軍に発破をかけてくれたり、
こう着状態でゲームがつまらなくなってくれば、積極的に攻撃して状況を動かしてくれたり、
フラッグを守って欲しいと言われれば、いつの間にか自軍アタッカーより奥深くまで侵攻して戦況をかき回してくれたり、
敵のフラッグに向かって無茶なスライディングをかました挙句古傷を痛め、相手チームにジュネーブ条約に基づく手厚い保護を受けたりと、
良くも悪くもゲームを盛り上げることに余念がない。
ゲーマーとしての手腕は高く、味方を指揮しながら進軍する隊長らしい戦法のほかにも、個人でのフラッグアタック、アンブッシュ、フラッグ防衛と、どんなシチュエーションもオールマイティーにこなしてくれる。
そのため、味方にすれば非常に安定感があるが、バイク事故で負った古傷のために全力疾走ができない、持ち込んだ銃が毎回必ず謎の故障を起こす、拠点を守っていたはずがいつの間にか前線に立っている、など、ゲームの手腕とはまったく別の部分で謎の不安定要素をもつ。
使用している装備は、オリーブドラブのBDU上下に同色のキラーキャップ、装具はベルトハーネスにまとめたマグポーチやダンプポーチと、軍装と言うよりはゲームに適した装備を堅実に選ぶタイプ。
しかし、既存の軍装を気にかけない自由な発想と、社会人であるが故の財力、常人離れした奇抜なセンスなどが相まって、使用する銃は徐々にイロモノ化していく傾向がある。
最近メインで使用している銃はマルイG36ベースのH&K-SL9
はじめのうちは普通のG36Cであったはずだが、ストックが変わり、長さが変わり、色が変わり、いつしかメカボ以外フルコンバージョンのビームライフルと化していた。
※その後、SL-9は二度ほど謎の故障を繰り返した後、再起不能となった。次に隊長が選んだメインウエポンは89式自動小銃。自衛隊の訓練に採用されるほどの堅牢さが、今度こそ隊長の呪いに打ち勝つことを祈るばかりである。
2011年02月11日
【コラム】MC51復活作戦! 三日目

さて、MC51のスコープの調整である。
いったい何が原因で、スコープはナナメについているのだろうか。
まずは、マウントリングに疑いの目を受けてみる。
ハイマウントリングを取り外し、ドラグノフに使用していたローマウントを取り付けてみる。
きつく固定し、試射。
すっ、と、弾はレティクルのほぼ中央から出現し、そのまままっすぐ、素直な弾道を描いた。
ビンゴだ。
どうやら、ハイマウントが傾きの原因だったらしい。

何かの拍子にゆがんだのか、もともとそうだったのかは分からない。しかし、二つのマウントリングを片手持ちで固定している関係上、ゆがみが出やすい構造ではあるのだろう。
なんにせよ、弾道の見え方がおかしいのはスコープのせいだったと判明した。
銃本体に目立った問題はなく。どころか、弾筋は素直そのものだ。
MC復活計画は、ひとまず成功、と言っていいだろう。
しかし、ゲームに持ち込むにはまだいくつか問題がある。
まずはスコープの高さだ。ローマウントを使用したことで、スコープのゆがみは解消されたものの、直銃床にローマウントベース&リングでは、さすがにアイラインが低すぎる。試射の際はシューティンググラスをかけていたから覗けたものの、ゲーム中、フルフェイスゴーグルをした状態では、とてもじゃないがスコープを覗き込むことはできない。
解決策は言うまでもなく、高いマウントリングか、マウントベースを手に入れることだ。
第二に、試射をしていて気づいたのだが、多弾装マガジンの調子がおかしい。どんなにゼンマイを巻き上げても、弾が数発しか上がってこないのだ。
このマガジンも、中学生の頃からずっと使い続けてきたのだから、不調も仕方がないと言ったところだろう。
一度ばらして、まずは様子を見てみようと思う。
多弾装マガジンは、弾と一緒に入り込んだ草や木の枝を気づかず巻き上げてしまい、給弾口を詰まらせてしまうことがある。
多弾装が不調なときは、まずは分解、清掃、注油だ。それで駄目なら、買い替えということになる。
今週12日には、チームメンバーで集まって、秋葉原へパーツ購入に出かける予定だ。
折もよいので、いろいろ揃えて来ようと思っている。
2011年02月10日
【コラム】MC51復活作戦! 二日目
さて、MC51復活計画。
二日目である。

強めのホップを解消するために、ストライクチャンバーをノーマルチャンバーに戻してみた。

これは別に、ストライクチャンバーを信用していないわけではなく(と、いうか、今回購入したパーツの中でいっとう高価なので、一番信じたいパーツだ)ただ単に、ホップパッキンのほうを戻そうにも、ノーマル品が既に破損しているからだ。
チャンバーをノーマルに戻し、改めて試射を行ってみると、ホップ最弱状態で手前に落ちるようなノンホップになった。
ホップの強くしていくと、フラットから浮き上がり気味のセッティングまで、欲しい弾道をすべて調整圏内に収めることができた。
わたしとしては、こちらのホップのほうがベターだ。
ストライクチャンバー自体が、強めのホップを想定して作られているのか、それとも、パッキンやシリンダーとの兼ね合いのせいかは分からないが、ともかく、わたしが組んだ感覚では、ストライクチャンバーは強めのホップセッティングになったことを記しておく。
しかし、ノーマルパッキンでは飛距離自体が少し落ちている感じはする。ストライクチャンバーでは、浮き上がり気味ではあったものの、もう一歩手前に弾が伸びる感じだったのだが……。
上手くセッティングすれば、ストライクチャンバーの弾の伸びと、ホップ設定範囲の両立ができるかもしれない。この辺は、また後々試してみたいと思う。
なんせ、高価なパーツだ。このまま捨てるのはもったいなさ過ぎる。
さて、ホップが安定したので、次はスコープを乗せて細かな調整をすることにした。
わたしはド近眼なので、サバゲの際にスコープは欠かせないのだ。
スコープを乗せて撃ってみると、おっそろしい弾道が見えた。
弾が、レティクルの左側から飛び込んできて、そのままスコープの右端へ、半ば前を横切るように飛んでいくのだ。
スコープのレティクルを、弾が飛び込んでくる左のほうへと動かしてみたが、調整ノブがギチギチになるまで回しても、まだ弾の出現するあたりに合わせることができない。
弾道がおかしいのかと思ってホップをいじってみるが、ホップを強くしようが弱くしようが、右から左へ飛んでいく弾道は変わらなかった。
当たらないときに、闇雲に撃つのは時間の無駄だ。
一旦銃を置いて、考えてみる。
弾が、左から右へカーブしているのだろうか?
しかし、それにしては全弾が、左から右に綺麗に飛んで行き過ぎる。
ホップが安定しないなら上下左右にもっと散るはずだし、もしホップの組みつけを間違って横回転がかかっているのなら、もっと大きくカーブしていくはずだ。
しかし、スコープなしでの弾道を見ている限り、あからさまに弾が曲がっている様子は見られない。
では、スコープの角度がおかしいのだろうか。しかし、スコープの上下範囲を、マウントに詰め物などをして調整することはあっても、左右の範囲を詰め物してまで調整するなんて聞いたことがない。
……ふと、スコープの角度で思い出した。
ドラグノフだ。
銃身直上にスコープが乗る銃で調整したスコープを、そのままドラグノフに乗せると、発射された弾がスコープの右端から飛び込んでくるように見える。
なぜなら、ドラグノフのスコープはレールの設計上、どうしてもやや左側にオフセットされる。すると、ドラグノフの銃身はスコープの中心線より右側にずれた状態になるから、発射された弾が、スコープの右端から飛び込んでくるように見えるのだ。


今のG3も、同じ様な状態にあるのではなかろうか。
弾が左端から飛び込んでくるのは、スコープの中心線が銃の右側にあるからだ。
では、弾が右端へ飛んでいく理由は?
弾が、スコープの中心線の左側から、右側へと横切るように飛んで行くからだ。
つまり、スコープの中心線そのものが、斜めにずれているのである。
だから、まっすぐ飛んでいるはずの弾が、大きく左から右へ、カーブしているように見えるのだ。

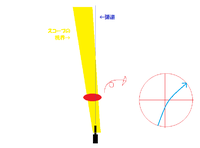
たしかに、フレームの上から見てみると、銃に対してスコープが、わずかにナナメについているように見える。
フレームの上ではわずかなズレでも、50メートル離れたら大きなズレだ。
これでは照準としては使い物にならない。
と、なると、どこを直せば解決するのだろう?
問題は、スコープを固定しているマウントリング、もしくはマウントベースにあるはずだ。
マウントリングには、M4用のハイマウントリング、マウントベースには、マグネシウムローマウントを使っている。
このどちらかがナナメについているせいで、スコープがナナメになっているのだ。
……だが、家に帰らなければ、代えのリングもマウントも無い。
今日はここまでにして、スコープの調整は明日考えることにしよう。
二日目である。

強めのホップを解消するために、ストライクチャンバーをノーマルチャンバーに戻してみた。

これは別に、ストライクチャンバーを信用していないわけではなく(と、いうか、今回購入したパーツの中でいっとう高価なので、一番信じたいパーツだ)ただ単に、ホップパッキンのほうを戻そうにも、ノーマル品が既に破損しているからだ。
チャンバーをノーマルに戻し、改めて試射を行ってみると、ホップ最弱状態で手前に落ちるようなノンホップになった。
ホップの強くしていくと、フラットから浮き上がり気味のセッティングまで、欲しい弾道をすべて調整圏内に収めることができた。
わたしとしては、こちらのホップのほうがベターだ。
ストライクチャンバー自体が、強めのホップを想定して作られているのか、それとも、パッキンやシリンダーとの兼ね合いのせいかは分からないが、ともかく、わたしが組んだ感覚では、ストライクチャンバーは強めのホップセッティングになったことを記しておく。
しかし、ノーマルパッキンでは飛距離自体が少し落ちている感じはする。ストライクチャンバーでは、浮き上がり気味ではあったものの、もう一歩手前に弾が伸びる感じだったのだが……。
上手くセッティングすれば、ストライクチャンバーの弾の伸びと、ホップ設定範囲の両立ができるかもしれない。この辺は、また後々試してみたいと思う。
なんせ、高価なパーツだ。このまま捨てるのはもったいなさ過ぎる。
さて、ホップが安定したので、次はスコープを乗せて細かな調整をすることにした。
わたしはド近眼なので、サバゲの際にスコープは欠かせないのだ。
スコープを乗せて撃ってみると、おっそろしい弾道が見えた。
弾が、レティクルの左側から飛び込んできて、そのままスコープの右端へ、半ば前を横切るように飛んでいくのだ。
スコープのレティクルを、弾が飛び込んでくる左のほうへと動かしてみたが、調整ノブがギチギチになるまで回しても、まだ弾の出現するあたりに合わせることができない。
弾道がおかしいのかと思ってホップをいじってみるが、ホップを強くしようが弱くしようが、右から左へ飛んでいく弾道は変わらなかった。
当たらないときに、闇雲に撃つのは時間の無駄だ。
一旦銃を置いて、考えてみる。
弾が、左から右へカーブしているのだろうか?
しかし、それにしては全弾が、左から右に綺麗に飛んで行き過ぎる。
ホップが安定しないなら上下左右にもっと散るはずだし、もしホップの組みつけを間違って横回転がかかっているのなら、もっと大きくカーブしていくはずだ。
しかし、スコープなしでの弾道を見ている限り、あからさまに弾が曲がっている様子は見られない。
では、スコープの角度がおかしいのだろうか。しかし、スコープの上下範囲を、マウントに詰め物などをして調整することはあっても、左右の範囲を詰め物してまで調整するなんて聞いたことがない。
……ふと、スコープの角度で思い出した。
ドラグノフだ。
銃身直上にスコープが乗る銃で調整したスコープを、そのままドラグノフに乗せると、発射された弾がスコープの右端から飛び込んでくるように見える。
なぜなら、ドラグノフのスコープはレールの設計上、どうしてもやや左側にオフセットされる。すると、ドラグノフの銃身はスコープの中心線より右側にずれた状態になるから、発射された弾が、スコープの右端から飛び込んでくるように見えるのだ。


今のG3も、同じ様な状態にあるのではなかろうか。
弾が左端から飛び込んでくるのは、スコープの中心線が銃の右側にあるからだ。
では、弾が右端へ飛んでいく理由は?
弾が、スコープの中心線の左側から、右側へと横切るように飛んで行くからだ。
つまり、スコープの中心線そのものが、斜めにずれているのである。
だから、まっすぐ飛んでいるはずの弾が、大きく左から右へ、カーブしているように見えるのだ。

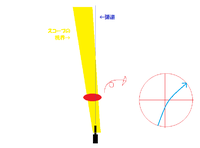
たしかに、フレームの上から見てみると、銃に対してスコープが、わずかにナナメについているように見える。
フレームの上ではわずかなズレでも、50メートル離れたら大きなズレだ。
これでは照準としては使い物にならない。
と、なると、どこを直せば解決するのだろう?
問題は、スコープを固定しているマウントリング、もしくはマウントベースにあるはずだ。
マウントリングには、M4用のハイマウントリング、マウントベースには、マグネシウムローマウントを使っている。
このどちらかがナナメについているせいで、スコープがナナメになっているのだ。
……だが、家に帰らなければ、代えのリングもマウントも無い。
今日はここまでにして、スコープの調整は明日考えることにしよう。
2011年02月09日
【コラム】MC51復活作戦!
本日、長らく眠らせていた電動ガンを復活させてみることにした。
わたしが人生ではじめて買った電動ガン、MC51だ。
購入したのは確か……中学生の頃だったろうか。まだ「18歳以下はエアガン所持禁止!」なんていう条例が、影も形もなかった頃の話だ。
MC51を購入後、落とし玉やわずかなおこづかいを貰うたびに、やりくりしながら固定ストックを買い、スプリングやシリンダーを入れ替え、細々と組み換えを楽しみながら使い続けてきた。
軽く取り回しやすく、多弾装で、当時「最強のゲームウエポン」と呼ばれていたMCは、最高の相棒だった。
ハイサイクルのG3SASが純正品で手に入る今では、信じられないことかもしれないが……。
けれど、いつしか本格的なサバイバルゲームをやるようになって、お金にも余裕ができて、新しい銃を次々買っていくうちに、MCの出番はどんどん減っていった。
やがてMCは部屋の片隅に眠っているか、さもなければ貸し出してしまうかで、自分で使うことはほとんどなくなってしまった……。
今回、現役復帰を目指して整備するのは、そんなMC51だ。
現在は、ウグイス隊長からもらったSG-1のフロントを組み込み、ロングバレル化したフルサイズG3になっている。
しかし、ロングバレル化したと言っても、中身はMCのまま。ショートバレル用の加速シリンダーではエア量が足りなかろうし、各部にも相当ガタが来ているだろう。
ためしに試射をしてみると、強めのホップをかければなんとか50メートルは飛ぶものの、弾に勢いがなく、着弾も散り気味だ。
当面の目標は、フルサイズのバレル長で1J近い初速と、ホップの安定化と言うことになるだろう。

あくまで目標は現役復帰なので、必要最低限のパーツを使って、箱だし新品のSG-1と同程度の性能まで持っていければ十分だ。
まずは、カスタムパーツの選定から始めることにする。
まず欲しいのは、加速スリットのないフルシリンダーだ。MCのショートバレルでは最適だった加速シリンダーも、500mm近いSG-1のバレルに合わせるにはエア量不足だからだ。
次に、長年の使用によってヘタっているであろう部分を考える。
まずはスプリング。一番負担がかかるパーツだ。とっくにヘタって、パワー低下の一因になっていることは間違いない。
そしてホップパッキン。磨耗しやすいゴムパーツ、それも、ちょっとした磨耗が性能に大きく影響するホップパッキンは、新調しておくに越したことはない。
スプリングは、初速調整を兼ねてライラクスのM90スプリング、ホップパッキンは、同じくライラクスのエアシールチャンバーパッキンのソフトを選択した。
チャンバーパッキンにエアシールを選んだのは、ホップを押すための虫ゴムが付属していたためだ。長年の使用で、ホップパッキンだけでなく虫ゴムも磨耗している可能性があったため、一緒に取り替えてしまいたかったのだ。
さて、こうしてカスタムパーツを選んでいると、ちょっと欲も出てくる。ノーマルよりもちょっとよくしたい。なんて思ってしまう。
そこで、ファーストのストライクチャンバーG3を組み込んでみることにした。M16用ストライクチャンバーが、かなり良い製品だと聞いていたからだ。
もともとホップの設計が良いG3に使って、効果があるかは分からないが、ものは試しだ。
パーツが到着したので、早速組んでみる。
G3の分解は慣れたものだ。さっさとメカボックスを取り出し、開ける。
数年間メンテナンスをしていなかった割には、メカボックス内は綺麗なものだった。
目立った汚れはグリスの黒ずみと、シリンダー内に付着した土などの細かなゴミくらいだ。
手早く掃除して、グリスアップする。基本的に、プラやゴムパーツにはシリコングリス、金属パーツにはモリブテングリスとオーソドックスな選択だが、シリンダー周辺には、マルイ製の高粘度グリスをたっぷりと塗布した。
気密がほしい部分には、とりあえずマルイの高粘度グリス使っとけ! と言うのがわたしの持論だ。
現在メインウエポンで使っているドラグノフは、シリンダーの気密が低いため、塗るグリスの種類によって初速も弾道もがらりと変わってしまう。
さまざまなグリスを試してみたが、もっとも高初速かつ優れた弾道安定性を発揮したのは、高粘度グリスを塗ったときだった。
たとえばシリコングリスと高粘度グリスでは、ドラグノフの初速が0.1J近くも違ったのだ。
そんなことがあって以来、わたしはシリンダー周りには必ず高粘度グリスを使う。
もっとも、ドラグノフと違ってMCは電動ガン。ピストンの往復回数がドラグノフの比じゃないので、負担になりすぎないよう、抵抗のでかいグリスは塗りすぎないよう注意する必要があるのだが。
組みなおす前に、加速シリンダーをフルシリンダーに、スプリングを新しいものに交換しておく。
下がり気味だった初速が、これで何とかなればいいのだが。

さて、ギアを収めてメカボックスを閉めようとすると、なかなか上手く入らない。よく見てみると、逆回転防止ラッチが上手くはまり込んでいなかった。
ほかのギアパーツは、きちんとガタツキなくはまり込むものだが、逆回転防止ラッチは構造上、どうしても浮き気味になってしまう。
メカボックスが上手くしまらないときは、ここをチェックしてみるといいだろう。ラッチの軸を、精密ドライバー等で外側からつついてやると、すんなりとはまってくれる。
あとは、タペットプレートがきちんとノズルと噛んでいるかも確認しておく。組みあげて一見ちゃんと動いていても、ノズルが動いていないせいで給弾が上手くいかないことがある。試射せずにゲームに持っていってから、それに気づいたりすると最悪だ。
……というのは、ウグイス隊長の実際の失敗談から学んでいるわけだが。
メカボックスが組みあがったら、次はチャンバーだ。
チャンバー一式を抜き取り、バレルを抜き取ってみると、ホップパッキンが案の定劣化しきっていた。半ば千切れている。

ホップパッキンを替える時には、新しいパッキンをぬるま湯で暖めて柔らかくしておくといい。硬いまま組み込んでゆがみが発生すると、せっかくのパッキンが台無しだ。
その後、パッキンの外側にシリコンオイルをたっぷりと吹き付ける。こうすることで、チャンバーに組み入れるとき、引っかからずに済むからだ。
抵抗の必要なゴムパーツに、オイルをつけまくるのには抵抗があるかもしれない。だが、抵抗の多いパーツだからこそ、組みつけの際に潤滑剤は不可欠だ。
まずはパッキンをオイルでべたべたにする気持ちで組み付けて、組み終わってから、いらないオイルを拭いて落とすくらいがちょうどいいだろう。

さらにストライクチャンバーを組み付けて、チャンバー周りも完成だ。

早速、野外で試射を行ってみた。
弾の伸びは素晴らしく、飛距離も目に見えて上がっている。
整備前は、山なりの弾道を描きながら50メートル付近で落ちていたのが、整備後は、50メートル付近までまっすぐ飛び、そこから浮き上がって山なりの弾道を描く感じだ。確実に一歩分飛距離が伸びている。
しかし……問題もある。
前述の、少し浮くような山なりのホップは、ホップ最低時のものだ。最低ホップが適正ホップでは、調整の幅がない。
どうも、パッキンのせいか、ストライクチャンバーのせいか、あるいはパーツ同士の相性か、ホップが強めになってしまっているようだ。
確かに、射程距離ぎりぎりの遠距離を狙うならば、今のホップセッティングで十分だ。
けれど状況によっては、飛距離は落ちてもまっすぐ飛んで欲しい場面もある。そういった時、弱ホップに切り替えられないのはちょっと使いづらい。
次のゲームは27日……それまでに、調整の幅があるセッティングを模索してみたい。
かつての相棒が、今の相棒へと返り咲いてくれるように、じっくり整備してやろうと思う。
おまけ。
G3のマガジンを入れるに当たって、AK用の81式弾帯を詰めてみた。

不要な部分を折り返して縫い付けただけだが、表から見た分には綺麗にできたように思う。

次のゲームに投入して、強度や使用感を確かめてみるつもりだ。
わたしが人生ではじめて買った電動ガン、MC51だ。
購入したのは確か……中学生の頃だったろうか。まだ「18歳以下はエアガン所持禁止!」なんていう条例が、影も形もなかった頃の話だ。
MC51を購入後、落とし玉やわずかなおこづかいを貰うたびに、やりくりしながら固定ストックを買い、スプリングやシリンダーを入れ替え、細々と組み換えを楽しみながら使い続けてきた。
軽く取り回しやすく、多弾装で、当時「最強のゲームウエポン」と呼ばれていたMCは、最高の相棒だった。
ハイサイクルのG3SASが純正品で手に入る今では、信じられないことかもしれないが……。
けれど、いつしか本格的なサバイバルゲームをやるようになって、お金にも余裕ができて、新しい銃を次々買っていくうちに、MCの出番はどんどん減っていった。
やがてMCは部屋の片隅に眠っているか、さもなければ貸し出してしまうかで、自分で使うことはほとんどなくなってしまった……。
今回、現役復帰を目指して整備するのは、そんなMC51だ。
現在は、ウグイス隊長からもらったSG-1のフロントを組み込み、ロングバレル化したフルサイズG3になっている。
しかし、ロングバレル化したと言っても、中身はMCのまま。ショートバレル用の加速シリンダーではエア量が足りなかろうし、各部にも相当ガタが来ているだろう。
ためしに試射をしてみると、強めのホップをかければなんとか50メートルは飛ぶものの、弾に勢いがなく、着弾も散り気味だ。
当面の目標は、フルサイズのバレル長で1J近い初速と、ホップの安定化と言うことになるだろう。

あくまで目標は現役復帰なので、必要最低限のパーツを使って、箱だし新品のSG-1と同程度の性能まで持っていければ十分だ。
まずは、カスタムパーツの選定から始めることにする。
まず欲しいのは、加速スリットのないフルシリンダーだ。MCのショートバレルでは最適だった加速シリンダーも、500mm近いSG-1のバレルに合わせるにはエア量不足だからだ。
次に、長年の使用によってヘタっているであろう部分を考える。
まずはスプリング。一番負担がかかるパーツだ。とっくにヘタって、パワー低下の一因になっていることは間違いない。
そしてホップパッキン。磨耗しやすいゴムパーツ、それも、ちょっとした磨耗が性能に大きく影響するホップパッキンは、新調しておくに越したことはない。
スプリングは、初速調整を兼ねてライラクスのM90スプリング、ホップパッキンは、同じくライラクスのエアシールチャンバーパッキンのソフトを選択した。
チャンバーパッキンにエアシールを選んだのは、ホップを押すための虫ゴムが付属していたためだ。長年の使用で、ホップパッキンだけでなく虫ゴムも磨耗している可能性があったため、一緒に取り替えてしまいたかったのだ。
さて、こうしてカスタムパーツを選んでいると、ちょっと欲も出てくる。ノーマルよりもちょっとよくしたい。なんて思ってしまう。
そこで、ファーストのストライクチャンバーG3を組み込んでみることにした。M16用ストライクチャンバーが、かなり良い製品だと聞いていたからだ。
もともとホップの設計が良いG3に使って、効果があるかは分からないが、ものは試しだ。
パーツが到着したので、早速組んでみる。
G3の分解は慣れたものだ。さっさとメカボックスを取り出し、開ける。
数年間メンテナンスをしていなかった割には、メカボックス内は綺麗なものだった。
目立った汚れはグリスの黒ずみと、シリンダー内に付着した土などの細かなゴミくらいだ。
手早く掃除して、グリスアップする。基本的に、プラやゴムパーツにはシリコングリス、金属パーツにはモリブテングリスとオーソドックスな選択だが、シリンダー周辺には、マルイ製の高粘度グリスをたっぷりと塗布した。
気密がほしい部分には、とりあえずマルイの高粘度グリス使っとけ! と言うのがわたしの持論だ。
現在メインウエポンで使っているドラグノフは、シリンダーの気密が低いため、塗るグリスの種類によって初速も弾道もがらりと変わってしまう。
さまざまなグリスを試してみたが、もっとも高初速かつ優れた弾道安定性を発揮したのは、高粘度グリスを塗ったときだった。
たとえばシリコングリスと高粘度グリスでは、ドラグノフの初速が0.1J近くも違ったのだ。
そんなことがあって以来、わたしはシリンダー周りには必ず高粘度グリスを使う。
もっとも、ドラグノフと違ってMCは電動ガン。ピストンの往復回数がドラグノフの比じゃないので、負担になりすぎないよう、抵抗のでかいグリスは塗りすぎないよう注意する必要があるのだが。
組みなおす前に、加速シリンダーをフルシリンダーに、スプリングを新しいものに交換しておく。
下がり気味だった初速が、これで何とかなればいいのだが。

さて、ギアを収めてメカボックスを閉めようとすると、なかなか上手く入らない。よく見てみると、逆回転防止ラッチが上手くはまり込んでいなかった。
ほかのギアパーツは、きちんとガタツキなくはまり込むものだが、逆回転防止ラッチは構造上、どうしても浮き気味になってしまう。
メカボックスが上手くしまらないときは、ここをチェックしてみるといいだろう。ラッチの軸を、精密ドライバー等で外側からつついてやると、すんなりとはまってくれる。
あとは、タペットプレートがきちんとノズルと噛んでいるかも確認しておく。組みあげて一見ちゃんと動いていても、ノズルが動いていないせいで給弾が上手くいかないことがある。試射せずにゲームに持っていってから、それに気づいたりすると最悪だ。
……というのは、ウグイス隊長の実際の失敗談から学んでいるわけだが。
メカボックスが組みあがったら、次はチャンバーだ。
チャンバー一式を抜き取り、バレルを抜き取ってみると、ホップパッキンが案の定劣化しきっていた。半ば千切れている。

ホップパッキンを替える時には、新しいパッキンをぬるま湯で暖めて柔らかくしておくといい。硬いまま組み込んでゆがみが発生すると、せっかくのパッキンが台無しだ。
その後、パッキンの外側にシリコンオイルをたっぷりと吹き付ける。こうすることで、チャンバーに組み入れるとき、引っかからずに済むからだ。
抵抗の必要なゴムパーツに、オイルをつけまくるのには抵抗があるかもしれない。だが、抵抗の多いパーツだからこそ、組みつけの際に潤滑剤は不可欠だ。
まずはパッキンをオイルでべたべたにする気持ちで組み付けて、組み終わってから、いらないオイルを拭いて落とすくらいがちょうどいいだろう。

さらにストライクチャンバーを組み付けて、チャンバー周りも完成だ。

早速、野外で試射を行ってみた。
弾の伸びは素晴らしく、飛距離も目に見えて上がっている。
整備前は、山なりの弾道を描きながら50メートル付近で落ちていたのが、整備後は、50メートル付近までまっすぐ飛び、そこから浮き上がって山なりの弾道を描く感じだ。確実に一歩分飛距離が伸びている。
しかし……問題もある。
前述の、少し浮くような山なりのホップは、ホップ最低時のものだ。最低ホップが適正ホップでは、調整の幅がない。
どうも、パッキンのせいか、ストライクチャンバーのせいか、あるいはパーツ同士の相性か、ホップが強めになってしまっているようだ。
確かに、射程距離ぎりぎりの遠距離を狙うならば、今のホップセッティングで十分だ。
けれど状況によっては、飛距離は落ちてもまっすぐ飛んで欲しい場面もある。そういった時、弱ホップに切り替えられないのはちょっと使いづらい。
次のゲームは27日……それまでに、調整の幅があるセッティングを模索してみたい。
かつての相棒が、今の相棒へと返り咲いてくれるように、じっくり整備してやろうと思う。
おまけ。
G3のマガジンを入れるに当たって、AK用の81式弾帯を詰めてみた。

不要な部分を折り返して縫い付けただけだが、表から見た分には綺麗にできたように思う。

次のゲームに投入して、強度や使用感を確かめてみるつもりだ。
